会社員時代には会社が支払っていた事業に必要な経費も、フリーランスになると自分で支払う必要があります。特に、居住と事業の両方で使用する住宅の家賃などの支出をどのように処理すれば良いか悩むこともあるでしょう。
この記事では、フリーランスが自宅を仕事場として利用する際の家賃の経費計上方法について解説しています。重要なポイントとして、家賃の算出方法や照明や駐車場料金など、他に経費として計上できる支出もまとめています。利用規約や資料の保管、月額の支払い記録も忘れずに。さらに、相談や参考になる情報も検索し、発生する費用を正確に処理するためのヒントを提供します。これからフリーランスになる方や、これまで家賃を経費計上していなかった方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
フリーランスが家賃を経費にできるケース

フリーランスは事業に関係するお金を経費計上できます。他に事務所などを借りず、自宅を作業場としている場合に限り計上できるのです。
賃貸の自宅を仕事場で使っている場合の家賃計上の条件

とはいえ、家賃全額を経費計上できるわけではありません。自宅の中でも事業に使用されている部分(空間、時間。以下同様)とプライベートに使用されている部分があるためです。
このうち経費計上できるのは事業に使用している部分のみとなります。
経費を計算する時には「家事按分」を活用する

家賃などの経費を事業に使用している部分と、プライベートに使用している部分に分けて計算することを「家事按分」といいます。家事按分の方法は大きく分けて二つあり、面積で按分する場合と時間で按分する場合です。
例えば、専有面積50㎡の物件に暮らしており、事業用に使用している部屋が10㎡だとすると、家賃のうち20%を経費計上できます。
時間で按分する場合例えば、1日の労働時間が8時間だとすると1日の1/3を事業で使用していることになります。しかし、事業で使用している時間に家族も家にいるなど、事業とプライベートが混在している時間がある場合にはさらに分ける必要があるでしょう。
家事按分の割合は決まっていません。フリーランスが個々の判断で根拠を持って割合を決めることになります。全額計上など明らかに不自然な割合だと、後に税務調査が入った場合におそらく指摘されるでしょう。多くのフリーランスは概ね家賃の30%〜40%となるようです。
特殊なケースですが、家族が経営している賃貸物件に住んでおり家賃を払っている場合は、経費計上できません。その理由は家族間の利益調整とみなされるためです。
家賃以外で家事按分にできる経費

それでは、家賃以外ではどのような経費が家事按分できるのでしょうか?一例を示します。
- 住宅(持ち家)の減価償却費、住宅ローン、固定資産税、管理費、火災保険料
- 住宅(賃貸)の更新料、礼金
※敷金や保証料は経費の対象とならない
- 電気代、ガス代、水道代(料理教室や食品製造など)
- PC、スマートフォン、タブレットなどの購入費用(業務で通信機器を使用する場合)
- インターネット代、携帯電話代(業務でインターネットを使用する場合)
- 自動車購入費用、自動車税、車庫証明手数料、車検費用など(業務で自動車を使用する場合)
いずれも業務で使用することが大前提です。デザイナーが業務中にコーヒーを飲むからといって、水道代やガス代を計上することはできません。また、同じライターでも取材で自動車を利用する方が自動車関連費用を計上するのは問題ありませんが、完全に在宅で対応可能な記事しか書かない方が自動車関連費用を計上することはできません。
フリーランスが経費を計上するには

フリーランスが経費計上するには確定申告が必要です。そして、確定申告をするには領収書やレシートの保存、そして帳簿付けが必要です。
2023年10月1日からはインボイス制度が運用開始となります。経費計上そのものはこれまでと変わらず可能ですが、インボイス登録した課税事業者が仕入額控除(消費税の控除)を受けるには、購入元の事業者もインボイス登録している必要がありますので注意してください。なお、家賃に消費税はかかりません(非課税)。
帳簿付けは本来なら複式簿記の知識が必要になります。しかし、近年では経費を入力して領収書やレシートのデータ(画像データを含む)を登録すれば帳簿付けをしてくれるクラウド会計サービスもあります。簿記の知識がない方は、このようなクラウド会計サービスを利用しましょう。
税務署は無作為に抽出した事業者に対して税務調査を行うことがあります。企業に比べて事業規模の小さいフリーランスが対象となる確率は低いかもしれません。しかし、仮に対象となったときに慌てないように、帳簿や領収書・レシートをすぐに閲覧できるようにしておく必要があります。
経費計上する費目や家事按分の割合は個々の判断に委ねられていますが、明らかに割合が高かったり、明らかに悪意があると感じられる場合には脱税とみなされます。その場合、懲役刑や罰金刑を課されたり、追徴課税の対象となったりする可能性があるため注意しておきましょう。
青色申告の為には個人事業主として開業届の提出が必要

確定申告には青色申告と白色申告の二種類があります。青色申告を利用するにはどのようにすれば良いのでしょうか?
確定申告するにはまず「個人事業の開業・廃業等届出書」(以下、開業届)を所管の税務署に提出する必要があります。開業届には次のような内容を記載します。
- 納税地(住所)
- 氏名
- 職業(事業内容)
- 屋号 など
また、開業届に加え「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。記載内容は開業届けとほぼ同じです。
これらの書類のフォーマットは税務署にあるため、手書きで記載して窓口に提出する他、クラウド会計サービス等を使用してオンラインで提出することも可能です。
青色申告には次のようなメリットがあります。
- 年間55万円の特別控除(e-taxにて確定申告する場合は65万円)
- 30万円未満の経費の一括計上(年間300万円まで)
- 赤字の繰越(最長3年)
白色申告では家事按分は活用できないのか
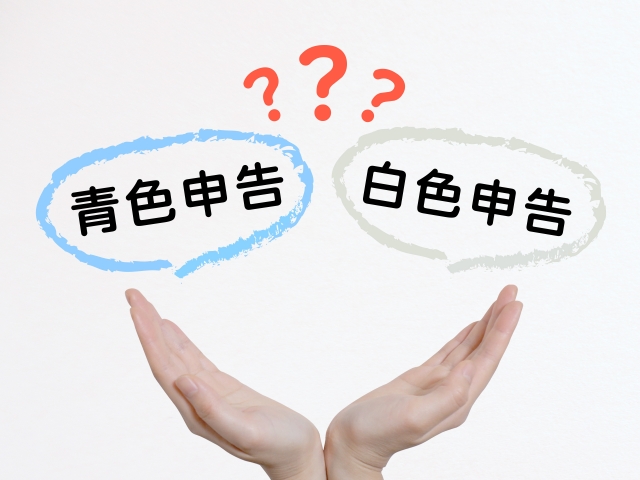
白色申告は青色申告より帳簿付けが簡素である代わりに、デメリットもあります。
白色申告で経費を家事按分するには、その割合が50%を超える必要があります(※1)。あるいは、事業用とプライベート用に完全に金額を区別できる必要があるのです。
スマートフォンやPCなら事業用とプライベート用を分ける(複数台所有)、家賃なら事業用スペースをパーテーションなどで区切ってプライベートには使用しないなど、煩雑になることは間違いないでしょう。
白色申告は、青色申告より帳簿付けが簡素ですが、そのメリットはクラウド会計サービス等を使うことで薄れてしまいます。また、前述のような青色申告にのみ適用されるメリットを享受できないため、あえて白色申告を選択する理由もそれほどないかもしれません。
(※1)国税庁「家事関連費(第1号関係)」
家賃を経費として計上してしっかり節税を

経費を計上できるのはフリーランスや個人事業主に与えられた会社員にはない特権です。決められたルールの中で、事業に使った経費を計上することでしっかり節税しましょう。
ただし、節税と脱税はまったく別のことです。言うまでもありませんが、脱税は犯罪行為ですので絶対に行ってはいけません。
最後に税金について少しお話しします。
税金は私たちが暮らす上で欠かせないものです。税金がなければ、誰も道路を整備してくれず、犯罪が横行しても誰も取り締まってくれず、大きな怪我をしても誰も病院まで運んでくれません(あるいは非常に高額な費用を請求されます)。
誰もが安心して暮らせる社会を作るためにも、社会人として事業者として、きちんと納税するようにしましょう。
投稿者プロフィール

- 12年の会社員経験(メーカーの機械設計など)を経てフリーライターになりました。会社員の良さ、フリーランスの良さそれぞれを実際に体験しています。記事執筆の他にインタビュー、取材(写真撮影含む)もできます。
最新の投稿
 How2024年3月20日知らなかったら損?フリーランスとして独立する前に準備するべきこととは?
How2024年3月20日知らなかったら損?フリーランスとして独立する前に準備するべきこととは? How2024年2月14日フリーランスになる前の準備とは?必要な手続きをご紹介します!
How2024年2月14日フリーランスになる前の準備とは?必要な手続きをご紹介します! How2024年1月13日フリーランスはどのようにタスク管理すればいい?タスク管理の本質とオススメ管理ツールを解説
How2024年1月13日フリーランスはどのようにタスク管理すればいい?タスク管理の本質とオススメ管理ツールを解説 Which2024年1月12日ギグワーカーとフリーランスの違いは何?スキルや専門性の違いを解説
Which2024年1月12日ギグワーカーとフリーランスの違いは何?スキルや専門性の違いを解説

コメント