フリーランスになって初めての年は確定申告や請求書作成など、やらなくてはいけないことが多くて悩んでしまうものです。特に請求書は作成方法や消費税を記載すべきなのか悩んでしまう人が多いです。フリーランスになる前に、事前情報としてフリーランスの請求書作成のポイントをおさえておきましょう。そこで今回は請求書を作成する方法や気をつけるべきポイント、インボイス制度についても解説します。
目次
フリーランスの請求書に消費税は必要?

フリーランスの請求書には、取引年月日や書類作成者の情報などが必要となりますが、仕事内容や数量、単価、金額の他に消費税の記載も必要となります。特に迷ってしまうのが税込みで記載するかどうかです。取引金額については、必ず税込みの金額を記載するようにしましょう。ただし、表示の仕方までは指定されていないため、仕事内容と同様に内訳が分かるようにするのが大切です。一般的には、税抜き金額と消費税額を記載し、最後に合計金額として税込み金額を記載します。会計ソフトを選ぶ際にも、消費税10%と軽減税率8%に対応しているものを選ぶことをおすすめします。
フリーランスの請求書の作成方法とポイント

フリーランスの請求書に消費税を記載しなければいけないことが分かったところで、請求書を作成する方法についてもチェックしておきましょう。気をつけるべきポイントについてもまとめているので、作成前に参考にしてみてください。
請求書番号を記載する
請求書には、請求書番号を記載するのが一般的です。請求書番号とは、請求書を管理するために付ける番号のことで、記載しなければいけないという決まりではありません。しかし、取引相手が多い場合や取引件数が多くなると管理が難しくなってしまうため、請求書番号を記載しておくと内容を確認したい時に役立ちます。初めのうちから請求書番号を記載して、管理しやすくしておくのがおすすめです。
振込手数料の負担について
一般的に、報酬を支払われる方法は振込が多いです。ただし、振り込みの場合には振込手数料が発生するため、振込手数料を先方が負担するのか自社が負担するのか明確にしておくといいでしょう。もしも、振込手数料が自社負担となる場合は、請求書に振込手数料の金額も記載しておくと自己管理しやすいです。先方も請求書を見れば確認をしやすいので、双方にとってメリットといえます。
源泉徴収金額について
源泉徴収制度とは、会社に属していないフリーランスが納めるべき所得税を取引相手のクライアントに天引きしてもらい、代わりに納税してもらう制度のことをいいます。基本的には、フリーランスは自ら所得税を申告して納付する「申告納税制度」を利用します。しかし、クライアントが報酬を支払う際に、所定の所得税の額を計算し、徴収して納付するケースがケースが増えています。フリーランスは仕事を請け負う際に、源泉徴収をしてもらうのか必ず確認をして取引を進めるようにしましょう。ただし、 源泉徴収税額は概算のため、納めすぎていた場合には、税金が還付されるので覚えておきましょう。源泉徴収には、対象になる仕事とそうでない仕事があります。対象になる仕事の代表例に、原稿の報酬やデザインの報酬などがあります。源泉徴収される額は、報酬のみが対象となります。1万円 × 10.21% = 1,021円となります。しかし、復興特別所得税額の関係で、報酬が100万円以下と100万円を超える場合で計算方法が異なるため、心配な方は専門のソフトを利用したり、税理士に相談することをおすすめします。
振込先を忘れないように
請求書に必要事項を記載できたら、振込先についてもクライアントに分かるように明記しておきましょう。振り込んで欲しい金融機関の情報や振込人名義や社名なども含めておくとよりクオリティの高い請求書となります。あわせて請求した日や振込期日なども書いておくと、お互い管理しやすいので、分かりやすい備考や請求書の冒頭に記載しておくのもおすすめです。
請求書への押印について
請求書への押印について必要かどうか悩む人も多いでしょう。厳密にいうと法律上、必ずしも必要なものではありません。しかし、取引先によっては社内規則で押印されていない請求書では、経理処理ができないケースもあります。そのため、事前に取引先に押印が必要かどうか確認しておくことをおすすめします。
フリーランスが納めるべき税金

フリーランスが納めるべき税金は、一つではありません。消費税の他にも納めなければいけない税金があるため、しっかりと理解しておきましょう。ここではフリーランスが納めるべき税金について解説していきます。
所得税
まずは個人事業主(個人事業者)として得た所得に対して国に支払う所得税です。会社員の場合には、毎月の給与から天引きされますが、フリーランスの場合には別途源泉徴収という形で国に納めています。具体的に治めるべき所得税の計算は、フリーランスとして得た収入から仕事上で発生した必要経費と各種控除を差し引いた「所得金額」を求めます。求める際の公式は以下の通りです。
所得税の算定基礎となる所得金額の算出方法
所得税の算定基礎となる所得金額 = 収入 - 必要経費 - 各種控除
なお、各種控除のうち、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が決まる「基礎控除」は、最大で48万円と設定されています。所得金額を確定させたら、課税対象となる所得金額に応じた税率を乗じて税額を算出していきます。例えば、1,000円〜1,949,000円の場合には5%の税率となり控除額は0円です。計算した額から控除額を差し引いたものが、納付すべき所得税の金額となります。納付する所得税額の算出方法や所得金額ごとの税率と控除額については、以下を参考にしてみてください。
納付する所得税額の算出方法
納付する所得税額 = 課税所得 × 税率 - 控除額
所得税率の速算表
| 課税対象の所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円〜1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円〜3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円〜6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円〜8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円〜17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円〜39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
上記の表からもお分かりの通り、所得税は、所得金額が大きくなればなるほど税率が高くなる累進課税制を採用しています。
なお、令和19年(2037年)までの期間については、所得税だけでなく「復興特別所得税」についても申告と納付をすることが義務付けられています。復興特別所得税とは、2011年に起こった東日本大震災の復興のため、必要となる施策財源徴収の税金のことをいいます。気になる税額は、その年に算出された基準所得金額の2.1%となっています。
住民税
次に都道府県と市区町村に支払う住民税です。「所得割」「均等割」の2つで構成されており、1枚の納付書で同時に支払うことができます。支払いには納期があり、6月末、8月末、10月末、翌1月末の年4回に設定されており、土日祝日が対象日だった場合には、次の平日が期限となります。
| 名称 | 要件 | 住民税額 |
| 所得割 | 前年の所得金額に応じて課税 | 課税所得の10%(都道府県4% + 市区町村6%) |
| 均等割 | 所得金額に関係なく定額で課税 | 4,000円(都道府県1,000円+市区町村3,000円) |
知っておきたい注意ポイントとしては、例え所得税が0円だったとしても、住民税がかかる場合がある点です。所得税と同様に、住民税にもその人自身に対する控除である「基礎控除」があり、所得税の基礎控除額は48万円、住民税の基礎控除額が43万円となっています。基礎控除範囲内の金額出なかった場合には、納税が必要となることは覚えておきましょう。
個人事業税
所得税や住民税の他にも、所得が290万円を超えた部分に対して事業の種類ごとに定められた3〜5%の税金を都道府県に支払う個人事業税を治めなければなりません。これは会社員の場合には支払う必要がない税金で、個人事業主として働くフリーランスならではの税金となります。個人事業税を納めなければいけない期限は、一般的に8月と11月の年2回となっております。
先でも紹介したように、個人事業税は事業の種類や職種ごとに税率がかわることや、業種によってはそもそも税率を支払う必要がない業種もあり、他の税金と比べて複雑だと感じる人が多いです。例えば、フリーランスの中でも人気のあるライターの場合、フリーランスライターだからこそ書ける独自性や芸術性がある文筆活動と認定されており、個人事業税がかからない業種の一つとされています。ただし、Webサイトに誘導したり広告を目的とした執筆活動や、商品やサービスの販売や宣伝を目的とした執筆活動であれば、「広告業」としてみなされ個人事業税として5%を課せられる可能性があります。他にも、デザインを行うWebデザイナーフリーランスやイラストレーターフリーランスも、「デザイン業」として5%を課せられる可能性があります。
フリーランスとしてこれから活動を考えている場合、収入額や職種によって個人事業税がかかることは覚えておきましょう。一般的にあまり知られていない税金の一つなので、収入が増えてきたときには、思わぬ出費を強いられることもあるため注意が必要です。納付期限も設定されているので、期限を過ぎないようにしましょう。
固定資産税
近年注目を集めているフリーランスは、自宅で好きな時間に仕事をする在宅可能な職種が多いです。自宅を仕事場にしている場合には、固定資産税も発生します。
例えば、自宅で仕事をしているフリーランスの場合、その自宅が持ち家かどうかがポイントになります。自宅が持ち家の場合には「固定資産税」がかかります。さらに、屋内以外にも、仕事で使用する建築物や機械、器具などの資産は償却資産として扱われ、固定資産税の課税対象となるので覚えておきましょう。
償却資産を所有していない場合には、固定資産税の申告なども不要となります。住んでいる地域の各自治体から納税額が記載された納付書が届くので、期限内に納付をすれば問題ありません。ちなみに、固定資産税の納期は原則6月、9月、12月、2月の年4回に分かれています。
特に、年が明けた1月1日時点で償却資産を持っている場合、フリーランスとして活動するための償却資産の評価額の合計が100万円以上、もしくは一つの償却資産の評価額が10万円以上の場合は1月31日までに申告が必要となるので注意してください。償却資産の合計額が150万円未満であれば償却資産税はかかりませんが、不安な方は税理士など専門家に相談して確認することをおすすめします。
消費税
フリーランスとして起業する場合には、消費税の納税義務が発生します。ただし、条件が設定されており、原則として課税される売上が1,000万円を超え、さらに「課税事業者」と区分された人に納税義務が発生します。加えて、消費税を支払う義務があるのか有無を判定する対象は
「2年前の課税売上」からとなります。そのため、起業してから2年間は原則「免税事業者」として扱われる為、消費税の納付義務は発生しないので、覚えておくといいでしょう。ただし、課税売上が1,000万円以上の場合には、例外となり消費税の納付義務は発生します。
消費税に関しては、今まで紹介してきた他の税金よりも納付金額が大きくなる傾向にあります。さらに、事業の売り上げが赤字であっても関係なく支払わなければならない税金であるため、消費税がかかる対象年度に入った場合には、納税準備預金を出費として計画に含んで予め準備をしておく必要があります。
なお、2023年10月に開始したインボイス制度に申し込み、課税事業者になった場合には、課税売上が1,000万円以下でも消費税の納税義務が発生します。意外と落とし穴になっているので、インボイス制度についても理解を含めておきましょう。
今回紹介したフリーランスが納めるべき税金は、それぞれ納期が異なります。申請が必要なものと必要がないものがあるため、詳細が知りたい場合には各自治体のサイトを確認するようにしましょう。もし自分で分からない場合には、自治体に問い合わせるか税理士さんに確認することをおすすめします。
インボイス制度で請求書の処理が変わった?

2023年10月よりインボイス制度が導入され、手続きを検討している人も多いのではないでしょうか。インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」と呼び、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式のことをいいます。一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存します。消費税の仕入税額控除が適用されますが、適格請求書が発行されていない場合には、消費税は仕入税額控除を受けることができないので注意が必要です。また、「1つの請求書につき、8%、10%の税率ごとに1回ずつ」のなど項目によって処理が必要となるため、請求書単位でそれぞれ端数処理を行わなければなりません。
まとめ
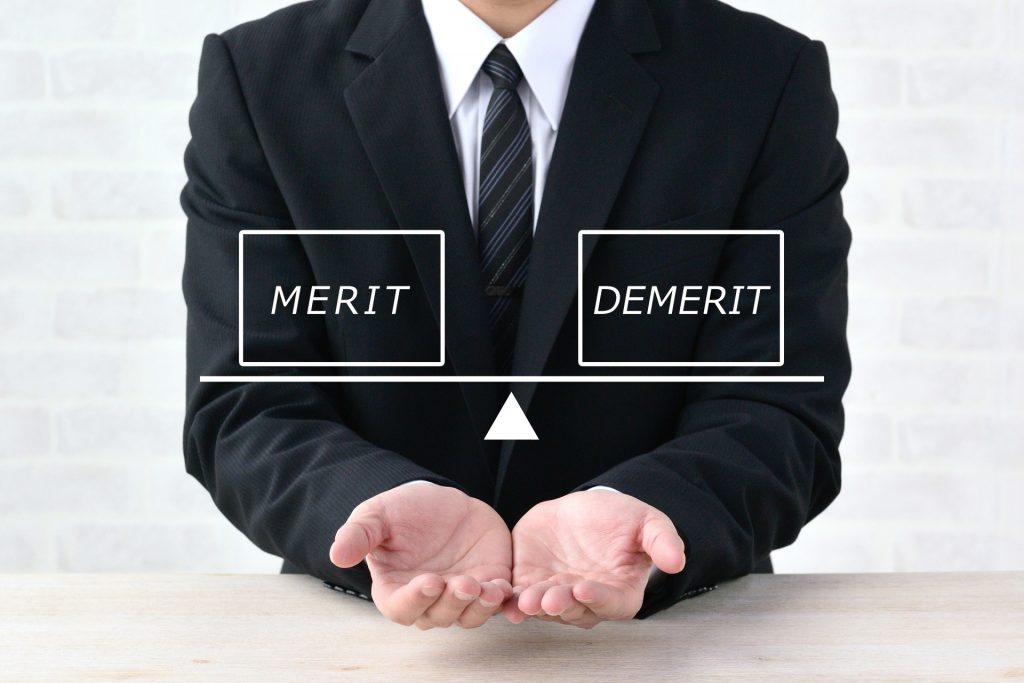
いかがでしたでしょうか。今回は請求書を作成する方法や気をつけるべきポイント、インボイス制度についても解説してきました。フリーランスで活動する場合には、消費税を記載している請求書を作成する必要があります。記載に厳密なルールはありませんが、仕事内容と同様に内訳が分かるように税抜き金額と消費税額を記載し、最後に合計金額として税込み金額を記載するのが一般的です。会計ソフトを選択する際にも、消費税10%と軽減税率8%に対応しているものを選ぶことをおすすめします。フリーランスが納めるべき税金に関しては、各書類や守らなければいけない納期もあり、管理に苦労しますがきちんと整理してこなしていきましょう。また、今回は請求書を作成する際に気をつけるべきポイントも紹介しているので、これから請求書を個人で作成しようと考えている方の参考になっていたら嬉しいです。
投稿者プロフィール
-
私は10年以上にわたり、デザイナーとしてのキャリアを積んできたフリーランスデザイナーです。デザインの魔法に魅了され、クリエイティブなアイデアを実現することが私の情熱です。
さまざまなデザインプロジェクトに携わり、ロゴ、ウェブ、印刷物、パッケージなど、多岐にわたる分野での経験を積んでいます。美しさと実用性を融合させ、クライアントのビジョンを実現するお手伝いを心から楽しんでいます。
クライアントとの協力を大切にし、オープンなコミュニケーションを通じて共にプロジェクトを築き上げます。納期を守り、高品質な成果物を提供することをお約束します。
私のデザインはビジネスに魅力を与え、ブランドを輝かせます。クリエイティブなアプローチと柔軟性を大切にし、クライアントの期待をいつも超えることを目指しています。一緒に素晴らしいプロジェクトを実現しましょう。





コメント