働き方を自由に選択できる時代になり、フリーランスも年々増加傾向にあります。働き方が自由になれば、当然、仕事を与える側も自由になります。ここで多くのフリーランスが業務委託契約に該当しています。委託するには委託したことを明確にしておく業務委託契約書が存在します。ところがフリーランスは業務委託契約書を取り交わしていない場合が多いのではないでしょうか。
実は業務委託契約書は法律上必須というわけではなく、契約書なしでも仕事ができてしまいます。
とはいえ、仕事はどうしても人の時間を消費しなければなりません。つまり、そこにはお金の問題が必ず発生します。
では、業務委託契約書の目的は一体何でしょうか?それは「言った、言わない」にならないよう、トラブルを未然に防ぐのに役立つのが業務委託契約書です。
この記事では業務委託契約書とはどんなものか、必要性はあるのかを詳しく解説していきます。お金が絡むことの知識は「知らなきゃ損」という言葉のとおりですから、契約時に何もわからない状態にならないようぜひ参考にしてみてください。
目次
フリーランスが結ぶ「業務委託契約書」

まずはじめに業務委託契約とは、自社の業務の一部を外部に委託するための契約です。委託側、受託側の区分が個人でも法人でも関係なく結ぶことができます。
業務委託契約書は法律外
業務委託契約書とは、その際の業務内容や条件等が記載された書面のことです。
一方、同じような言葉に「雇用契約書」があります。雇用契約は、雇い主からの命令や指示においてある程度の拘束力が生じるのに対し、業務委託契約の場合はあくまでも個人と事業者それぞれ独立した立場での契約ということになります。雇用関係は発生しません。
そのため、雇用契約書には民法や労働基準法に基づき作成されることが主となっている一方、業務委託契約書の場合には、内容については委託側が自由に決めることができるものです。
なお、業務委託契約書も雇用契約書も作成が法律で義務付けられているものではありません。したがって、契約を締結する際には、自分の希望する条件に当てはまっているなど、しっかりと内容の把握と理解をしたうえで進めることが重要となります。
業務委託契約のメリット
業務委託契約を活用する委託側のメリットとして、人材教育コストの削減、納期の速さが挙げられます。一から求人募集をかけて採用し、その人にお任せで業務がこなせるようになるまで膨大な労力と時間がかかります。したがってスポット的にプロに任せられることはかなりのメリットとなります。逆から見れば受託側からの価格交渉がしやすくなるのもポイントです。
業務委託契約書にも種類がある
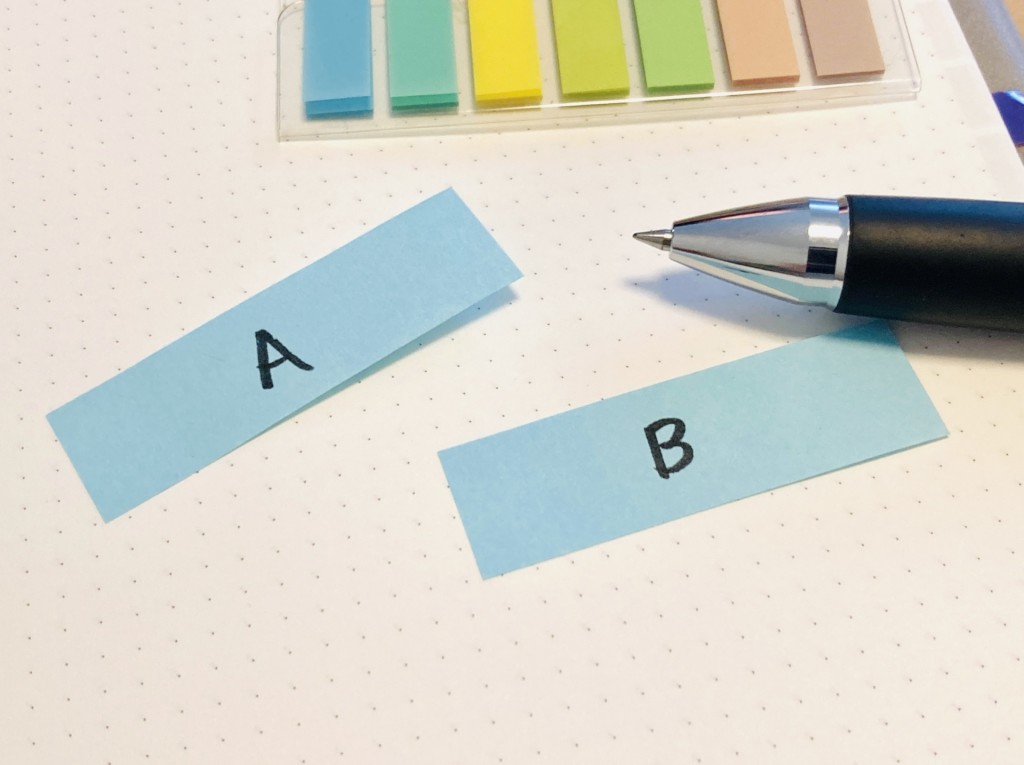
業務委託契約書には3つの種類があります。
1つずつ見ていきましょう。
毎月定額制
その名の通り、毎月一定額を支払うという契約の際に用いるものです。
フリーランス側から見ると、毎月決まった額が支払われるため、収入が安定するというメリットがあります。
成果報酬型
仕事の成果に応じて報酬の変動がある場合の契約です。
高い成果を上げれば報酬が上がることから、業務に対するモチベーションを高く維持することができるでしょう。一方、成果が出ないと報酬に繋がらないためリスクがあるとも言えます。
単発業務型
仕事一つ一つに報酬が確定しており、仕事ごとに契約を結んでいくものです。
成果報酬型のように結果が出るまで報酬が決まらないという心配はありませんが、1件ごとに契約を結んでいかなければならないため、仕事の選別と契約にかかる一定の手間がデメリットです。
なぜ業務委託契約書を結ぶ必要があるのか
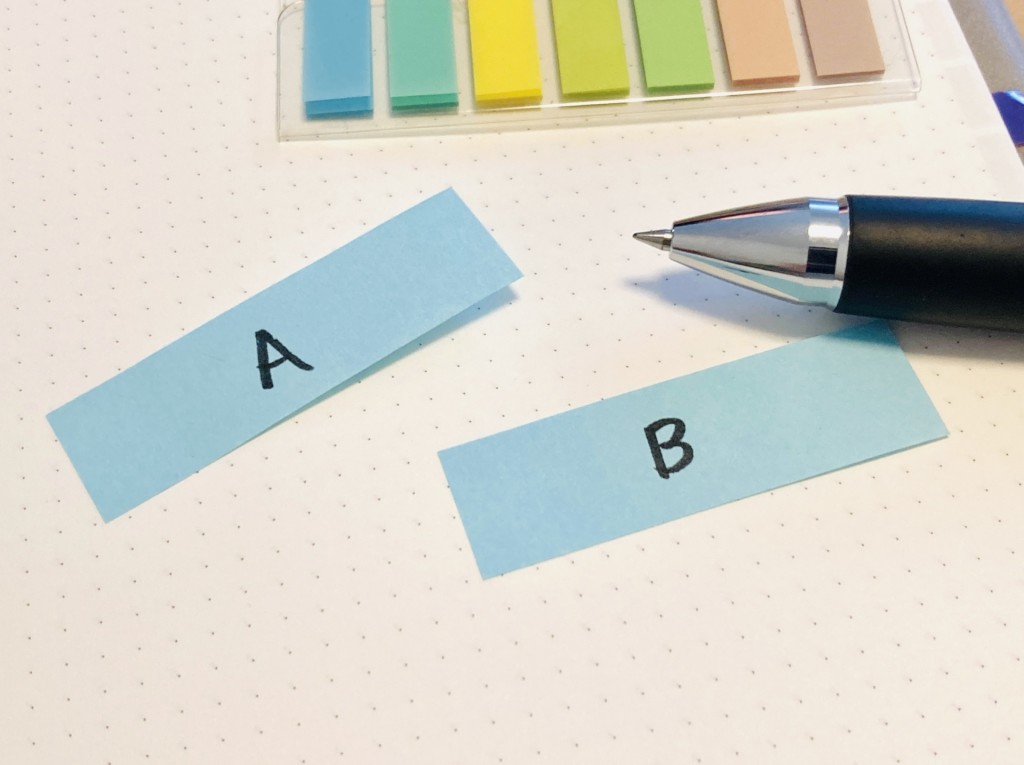
必ずしも必要ではない業務委託契約書ではありますが、やはり契約を結ぶ上では必要だといえます。
というのも、口頭での契約となると後々言った言わないというトラブルに発展してしまう可能性があるためです。
契約書があれば、そのような問題を避けることができ、お互いに契約時の内容を随時確認しあうことが可能です。仮にトラブルが発生して裁判という話になった場合にも、業務委託契約書が証拠として役立ち、正確に契約内容の詳細を示すことができます。
また、何よりお互いが疑念を抱くことなく安心して契約を結ぶといった信頼関係を築く上でも業務委託契約書は大きな役割を果たしてくれるといえます。
業務委託契約書に記載する項目

業務委託契約書に記載すべき項目は下記のとおりです。
1,業務内容
2,契約形態
3,契約期間
4,報酬
5,支払条件
6,秘密保持
7,契約解除の条件
8,成果物の権利
9,禁止事項
10,契約不適合責任
8個目の「成果物の権利」とは、完成した成果物に関して、著作権や知的財産権を保持するかどうかを記載するものです。
10個目の「契約不適合責任」とは、完成された成果物が基準に達しなかった場合に、報酬の減額や契約解除等の責任を負うという点を記載するものです。
契約形態の違い
業務委託には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3種類の形態があります。
一つ目の請負契約とは、成果物を完成させることが条件である契約です。
ライターやエンジニアの仕事などの際に結ばれる契約です。
請負契約の場合は、完成した成果物の対価として報酬が発生しますから、未完成の場合には報酬を受け取ることができません。
次に委任契約とは、法律に関する業務を委託する契約です。
例えば、弁護士依頼や税理士への確定申告依頼などがこれにあたります。
委任契約の場合、業務を行うことの対価として報酬が発生しますから、成果物の有無は問われません。
最後に準委任契約とは、法律以外に関する事務を委託する契約です。
コンサルティングやセミナー講師依頼などがこれにあたります。
こちらも委任契約同様に、業務を行うことの対価として報酬が発生します。
リスク回避のために注意しておくこと

続いては、業務委託契約を結ぶ際に気を付けるべきポイントをご紹介していきましょう。
業務委託で人気のある職種
例えば営業、マーケター、ライター、デザイナー、プログラマーなどがあります。
フリーランスとして業務委託契約を結ぶ場合、委託先が不安に思っていることを払拭するような働きかけができるかがポイントです。委託先がリスクとして気にしている部分についてこまめな報告を行ったり、オープンにして情報提供・情報共有をしながら仕事に取り組めると信頼関係を築きやすくなります。
営業
特に営業は場数が必要で、育成が大変な職種のひとつです。そのため、自社の社員教育よりコストパフォーマンスがよいと判断した企業が依頼をします。
リスクとしては成果の見えづらさや報酬の設定しづらさが挙げられます。
マーケター
web広告とSNSが主流になり、多くの企業が取り入れているため、需要が高い職種になってきています。大手広告代理店に入社せずともフリーランスとして活躍できる受託側と、大手広告代理店よりコストパフォーマンスに優れたフリーランスを利用したい委託側とでマッチしていると言えます。
リスクとしては成果の見えづらさや報酬の設定しづらさが挙げられます。
ライター
多くの場合、請負契約になるでしょう。委託側としては業務内容が明確なので仕事を振りやすいです。報酬額は文字単価で決まるのが通例となっています。初期投資費用や維持管理費がほとんどかからず、事業税を取られないこともあり、人気が高い職種のひとつとなっています。
リスクとしては他者の丸コピーなどの著作権侵害などが挙げられます。
デザイナー
こちらも請負契約になるでしょう。デザイナーと言ってもさまざまで、webサイト、広告、チラシ、ロゴなど多岐にわたります。webサイトですと若干プログラマー寄りになります。
リスクとしては他者デザインの意匠権侵害などが挙げられます。
プログラマー
請負契約と準委任契約が想定されます。複数人でひとつのものを完成させるプロジェクトであれば、期間を定められることが多いでしょう。ツールを作ってそれを納める場合ですと、成果物扱いになるので請負契約になります。
リスクとしてはバグや不具合による損害賠償などが挙げられます。
注意すべき事項
契約形態
説明したとおりですが「請負契約」または「委任契約・準委任契約」いずれかによって報酬発生条件が異なります。業務内容と合わせて適切な契約を選択します。
業務内容の詳細
業務委託契約書には業務内容の詳細を明確にしておく必要があります。
そうすることで、トラブルなどに発展することを未然に防ぐことができるからです。
気になる点や、不安要素がある場合には、契約前に必ず確認しておきましょう。
有効期限
業務契約書の有効期限は、成果物を納品して終了するという場合と、期間を設けての契約とし、有効期限後に自動更新の条項が定められるというものがあります。
どちらの契約形態になっているのかをあらかじめ確認しておきましょう。
報酬の支払い
報酬の金額や支払日、支払い方法の確認をします。
特に請負契約の場合には、いつ、どのタイミングで、どういった形での納品をすることで、など、具体的に記載されていることで認識のズレなどを防ぐことができます。
納品後の検収期間についても支払期日に影響してくるものであるため、確認が必要です。
また、支払いタイミングは締めのタイミング等で大きく変わってくるもので、収入に関わる重要な部分なのでしっかりと把握しておく必要があります。
経費の扱い
業務遂行に関わる経費をどこまで請求できるかどうかを確認しておきます。
経費として認められるものが少なく自己負担が増えてしまうと想定よりも収入減になってしまいます。
契約ごとに経費の範囲は異なってきますので、確実に確認しておきましょう。
途中解約
委託側は本来支払うはずだった業務委託料を受託側に支払うことと引き換えにいつでも契約の解除ができるとされています(民法第641条)。
例えば案件が委託側の事情で頓挫したときなどです。また受託側の要因で解除の可能性もありえます。受託側が体調不良で仕事を続けられなくなった、委託側に大きな損害を被るほどの行為が受託側で見受けられたときもです。解除を持ちかけたほうの一方的な理由の場合、違約金が発生する契約が一般的です。
この場合に、どこまでの報酬を受け取ることができるのか、どの程度事前に通知をする必要があるのかなどに関しても確認しておきましょう。
業務委託はその契約形態や案件によって契約期間はさまざまです。
例えば請負契約の場合、納期の問題があるにせよ、成果物が完成するまで契約は続きます。準委任契約の場合、プロジェクト案件であればそのプロジェクトが完了しなければ契約終了にはなりません。
3年で職場を変えなければいけない派遣契約とは異なり、業務委託に契約期間の上限はないため、契約の更新はなく、もし当初の予定より延長になる場合は再度契約し直すことになるでしょう。メンテナンス系など長期でサポートが必要な職種の場合は、何度も再契約をする手間を省くため自動更新契約を相談されることもあります。
その他各事項の確認
知的財産権、秘密保持条項、所轄裁判所、損害賠償、契約不適合責任などの条項に関しては、一方的に不利になることのない内容となっているかの確認が必要です。
一つ一つの事項に関して確認し、希望する変更点などがある場合に関しては契約前に交渉していきましょう。
業務委託契約書の作成は2パターン
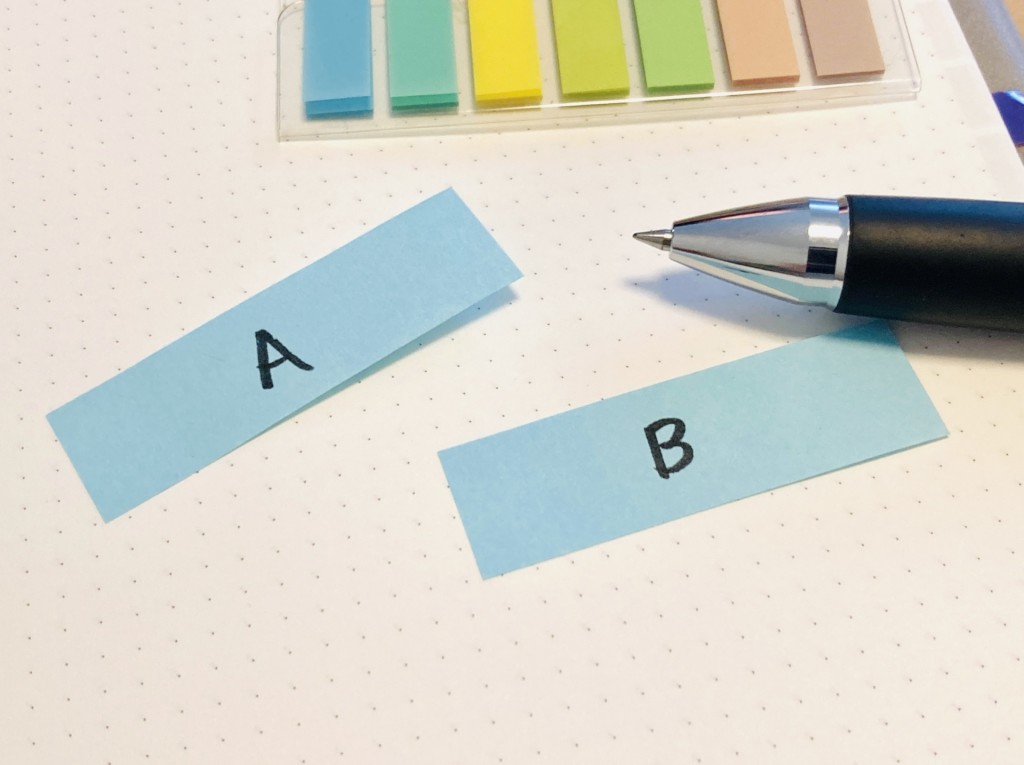
続いて、実際に業務委託契約書を作成について説明していきましょう。
作成には大きく分けて「クライアント(委託)側」「フリーランス(受託)側」の2パターンがあります。どちらにせよ、委託側、受託側双方に手間が発生することを理解しておきましょう。
クライアント側が作成
委託側が作成した業務委託契約書に関しては、先ほどお伝えした「リスク回避のために注意しておくこと」に注意しながら内容を確認していく必要があります。
一つ一つ確認するには労力がかかりますが、契約書にサインをすると後々知らなかったではすまされないこととなってしまいますので、確実に内容を理解したうえでサインをしましょう。
フリーランス側が作成
請負側が作成するという場合もありますが、基本的には作成時に関しても気を付けるべきポイントは変わりません。
しかしながら、業務委託契約書は必要事項全部を網羅しておくことが必要となります。
初めて作成するという場合や、大きな契約の場合などには弁護士などに相談して作成することをおすすめします。
主流になりつつある電子契約とは?

電子契約書は、紙と同様の証拠力が認められており、電子データの中に電子署名や電子サインをすることで改ざんや紛失のリスクを避けることができます。セキュリティの高いクラウドサービスを利用しているツールが増えています。
また、電子契約を導入すると手続きの手間が省けます。例えば契約書の送付をインターネットでおこなうことで、郵送の手間と時間をカットしたり、すり合わせを行う際も都度対面で取り交わす必要がありません。さらに電子契約用のツールは検索機能を盛り込んでいるものもあるので、探す手間も省けます。
こういった意味で、電子契約のメリットは大きいと言えるでしょう。
以下に電子契約サービスやツールを選ぶ際のポイントをいくつか挙げてみました。
・従量課金制または定額制
・テンプレートの充実性
・紙媒体も電子媒体も一元管理
・電子サイン送信数の制限
・ワークフロー機能
・サポートの手厚さ
お試し無料プランで提供してくれる場合はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。
フリーランスで活動する際の注意点
社会的信用度が低いのは受け入れる
よく聞く社会的信用度とは簡単に言えば収入の安定性と後ろ盾の有無です。フリーランスは企業に属さないため、身元の保証がなく、毎月同じ収入があるわけではないからです。これは現代日本においてフリーランスの宿命であり受け入れなければならない事実です。委託側から見ても、対企業か対フリーランスかによって、恐らく身構え方が違うでしょう。ただ、フリーランスだからこその柔軟な対応力、障壁のないコミュニケーション環境は需要の高いセールスポイントとなります。
より安定した収入を得たい場合は、なるべく長期で契約できるように、プロジェクト案件に積極的にアプローチしたり、契約時には契約終了後のことも考えて、委託側に今後の仕事について相談してみるのもよいでしょう。
インボイス制度への対応
インボイスと業務委託契約は直接的な関係はありませんが、委託側に安心感を与えるための重要なポイントとも言えるでしょう。
インボイス制度が始まる前、委託側は仕入額控除を利用して、受託側に支払った消費税を控除していました。ところが受託側は売上1,000万円を超えなければ免税事業者として扱われ、受け取った消費税を納税しなくてもよかったのです。簡単に言うと消費税が丸ごと受託側の懐に入ったわけです。
しかし、インボイス制度が始まってからは、委託側はインボイスがないと仕入額控除ができなくなり、受託側が免税業者である場合、委託側にとって消費税の払い損というデメリットが出てきました。したがって委託側は適格請求書発行業者と取引をしたいと思うはずです。
こうなると、受託側にとっては取引内容にも少なからず影響が出る可能性があります。例えば消費税分を差し引いて報酬額を設定したり、取引数自体を減らされるケースも考えられます。インボイス制度はそもそも、回収できていたはずの消費税を正しく回収できるようにするために導入された制度です。したがって、正しく納税できるように、受託側が適格請求書発行業者になるのが本来の姿です。
インボイス制度に対応していれば、委託側は安心して契約を結べることに繋がるのではないでしょうか。
まとめ
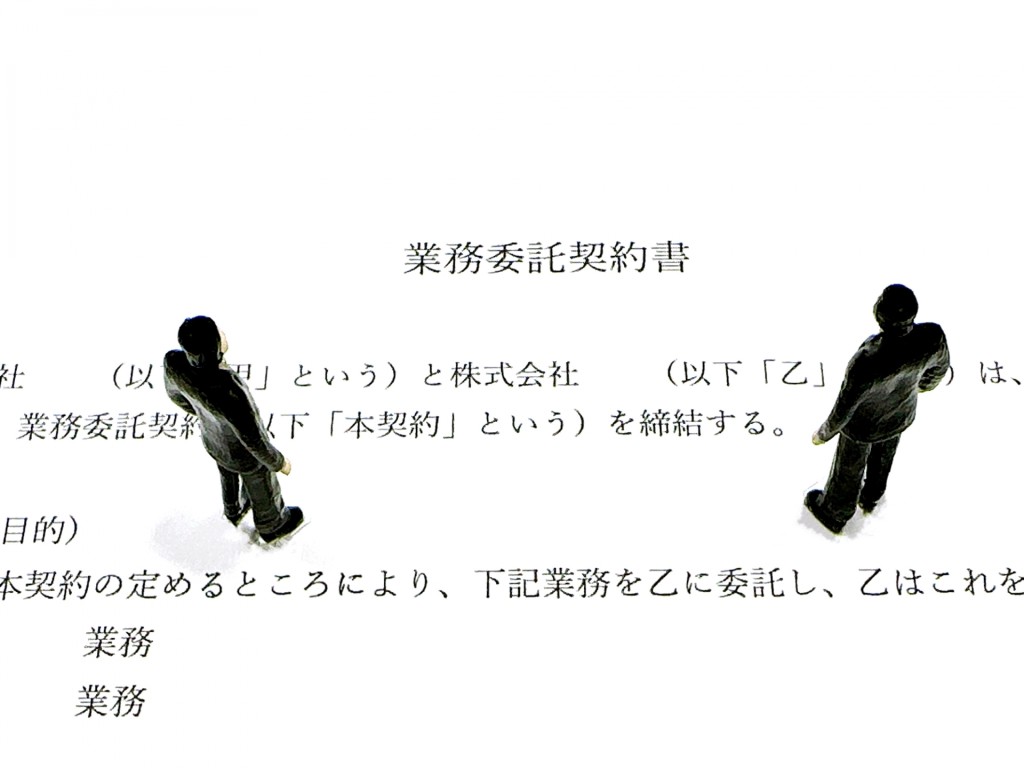
以上、フリーランスが業務委託契約書を用いて契約を結ぶ場合に気を付けたいポイントなどについて解説してきましたがいかがだったでしょうか?
業務委託契約書は法律上必須のものではありませんが、あることで円滑に業務をすすめることができます。締結の際には自分の納得のいく内容であるかをしっかりと確認することが重要になります。
投稿者プロフィール
-
私は10年以上にわたり、デザイナーとしてのキャリアを積んできたフリーランスデザイナーです。デザインの魔法に魅了され、クリエイティブなアイデアを実現することが私の情熱です。
さまざまなデザインプロジェクトに携わり、ロゴ、ウェブ、印刷物、パッケージなど、多岐にわたる分野での経験を積んでいます。美しさと実用性を融合させ、クライアントのビジョンを実現するお手伝いを心から楽しんでいます。
クライアントとの協力を大切にし、オープンなコミュニケーションを通じて共にプロジェクトを築き上げます。納期を守り、高品質な成果物を提供することをお約束します。
私のデザインはビジネスに魅力を与え、ブランドを輝かせます。クリエイティブなアプローチと柔軟性を大切にし、クライアントの期待をいつも超えることを目指しています。一緒に素晴らしいプロジェクトを実現しましょう。





コメント